 |
新版
日本人はなぜ
成熟できないのか |
大人の対応ができる国 ドイツ/幼児思考の抜けない日本
---- 歯に衣着せぬ辛口討論、本音対話 !
●不幸はれっきとした私有財産 (曽野綾子)
●「戦争」がドイツを大人にした (クライン孝子)
●教育は強制から始まる (曽野綾子)
●うそのつき方を教えるドイツの親 (クライン孝子)
●人間は平等でも公平でもない (曽野綾子)
●ドイツに落ちこぼれはいない (クライン孝子)
●愛国心は身を守る必需品 (曽野綾子)
●子供の国から大人の国へ (クライン孝子)
|
海竜社
2014年7月 |
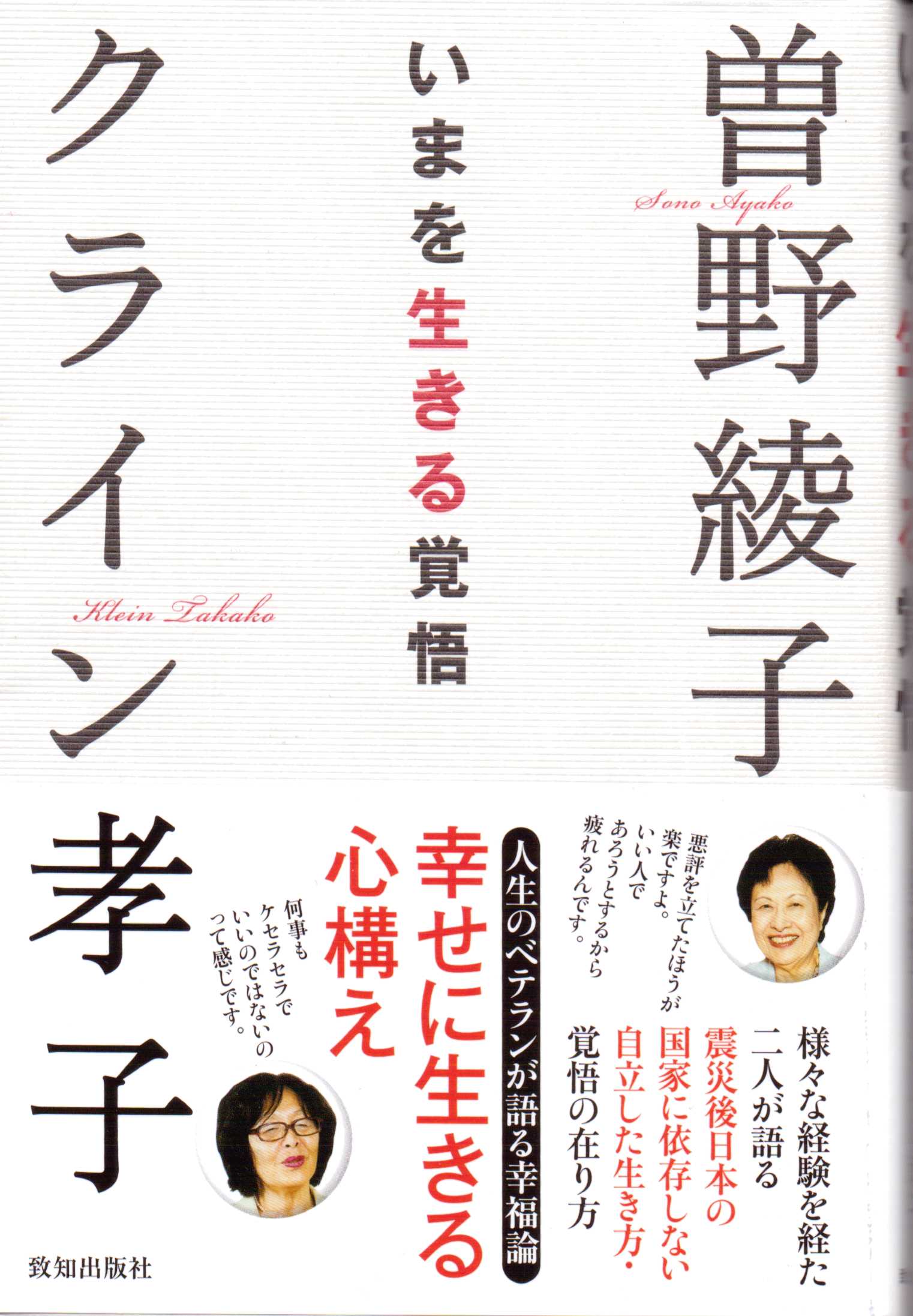 |
いまを生きる覚悟
|
●様々な経験を経た二人が語る震災後日本の国家に依存しない自立した生き方・覚悟の在り方
●人生のベテランが語る幸福論
●幸せに生きる心構え
「悪評を立てたほうが楽でいいですよ。いい人であろうとするから疲れるんです。」(曽野)
「何事もケセラセラでいいのではないのって感じです。」(クライン)
|
致知出版社
2012年3月 |
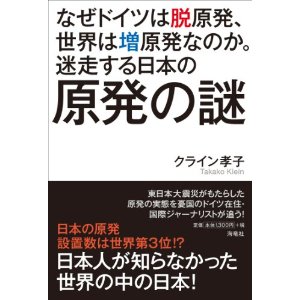 |
なぜドイツは脱原発、
世界は増原発なのか。
迷走する日本の
原発の謎
|
東日本大震災がもたらした原発の実態を憂国のドイツ在住・国際ジャーナリストが追う!
日本の原発 設置数は世界3位!?日本人が知らなかった世界の中の日本!
●3.11以降明らかになった"世界から取り残される"日本
●誰も止められなかった唯一の被爆国日本の原発事故
●福島原発事故を引き起こした悪しき日本の構造
●世界を揺るがすドイツの「脱原発政策」事情
●福島の"後"も世界での原発推進の空気は衰えない
●エネルギー獲得競争に翻弄された世界史
●ご先祖様の遺言がドイツを「脱原発」に踏み切らせた
●日本は原発とどう向き合うべきか |
海竜社
2011年9月 |
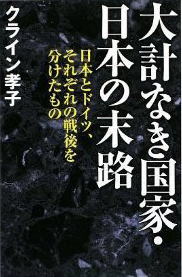 |
大計なき国家・日本の末路
日本とドイツ、それぞれの戦後を分けたもの |
周辺国との関係を修復し、ロシアとも巧みに連携をはかり、いまやEUの実質的中心国としてゆるぎない存在感を見せつけるドイツ。それに対して、アジアにおいても世界においても、その存在感がますます希薄になりつつある日本。その差はどこから生じたのか。戦後補償、周辺国との関係、領土問題、再軍備、歴史教育、情報機関、メディア、政治家など、それぞれのテーマで日独の戦後60余年を比較検証し、現在の日本の問題を浮き彫りにする。
|
祥伝社
2009年10月 |
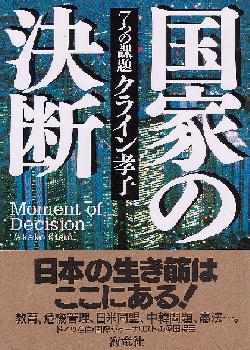 |
国家の決断
7つの課題 |
教育、危機管理、日米同盟、中韓問題、憲法…。日本の常識は世界の非常識、日本の生き筋はここにある!
日本人が気づかない日本の問題点に、ドイツ在住のジャーナリストが鋭く迫る。
|
海竜社
2006年3月 |
 |
拉被害者を放置した日本
国をあげて取り戻したドイツ
拉致! |
これでも日本は国家か?
この通哭の悲劇に遭遇した日本とドイツ。
二つの国家の対処の仕方から浮かび上がってきたものは・・・。
ドイツ在住の異色のジャーナリストが独自の視点で切り込んだ驚愕の人間ドラマ!
赦されざる国家の無力!
怒りの告発!! |
海竜社
2003年12月 |
 |
なぜ日本人は
成熟できないのか
|
与えられるよりは与えることを
理解されるよりは理解することを・・・
●不幸はれっきとした私有財産(曽野綾子)
●無邪気なお人よしのままで大丈夫?(クライン孝子)
●教育は強制から始まる(曽野綾子)
●嘘のつき方を教えるドイツの親(クライン孝子)
●人間は平等でも公平でもない(曽野綾子)
●好きこそ物の上手なれ−マイスター制度(クライン孝子)
●与えることが大人への道(曽野綾子)
●老いも若きも奉仕する(クライン孝子)
|
海竜社
2003年4月 |
 |
「対話」劣等生の
眠たい日本人
|
あなたは、心から対話したことがありますか?
「対話のない会社は生き残れない」
「ネットの時代だからこそ、面と向って話し合うことが大切」
「消費者として欠かせない対話能力」
「対話は自立へのプロセス」
・・
ビジネスの現場でも家庭でも消費者としても、これからは「対話能力」がものをいう時代になる。
|
ポプラ社
2002年9月 |
|
「世界の中の日本」
共著
|
|
拓殖大学
広報室 |
 |
お人好しの日本人
したたかなドイツ人
好評発売中
|
ひとの生き方は、国の生き方である。
いつから日本人は信念を貫く力、先を読む力、洞察する力、疑う力を失ったのか?
百戦錬磨のヨーローッパから、愛する日本へ警鐘を鳴らす。
|
海竜社
2001年5月 |
|
日本・百年の針路
「繁栄・平和・幸福・自由」
への戦略
(51人の中の一人)
PHP研究所副社長江口克彦「編」
|
誇り高く、力強く生きるための叡智。
尊敬を集める国家への戦略。
この国を代表する政治家・経済人・学者・評論家51人が描き出す、日本そして日本人の進むべき道。 |
PHP研究所 |
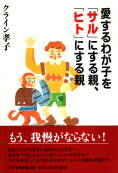 |
愛するわが子を
「サル」にする親
「ヒト」にする親
|
叱ることができない日本の大人たちへ
彼らを「サル」にしてしまっていいのですか?子供を正しくしつけるためのヒントと心構えを明かす。 |
PHP研究所
2001年 3月 |
 |
「捨てない生活」
-快適なドイツ流ライフスタイル−
|
自転車は50年経っても修理して使い包装紙は何度でも再利用
そんなドイツの無駄のない生活はどうして成り立つのか。日本と何が違うのか。 |
ポプラ社
2001年2月 |
 |
「歯がゆい日本国憲法」-
なぜドイツは46回も改正できたのか
|
竹村健一氏感嘆!
「初めて客観的に語られる憲法論」
改憲のたびに世界の信頼を得るドイツ
では、日本はどうするか! |
祥伝社
2000年7月 |
 |
「甘やかされすぎるこどもたち」
|
日本人とドイツ人の生き方
受験がいっさいないドイツ
なぜ? |
ポプラ社
1999年10月 |
 |
「歯がゆいサラリーマン大国・
日本」
|
なぜドイツは不況にも動じないのか?
充実した休暇・手厚い失業保険豊かな老後…
ドイツにできて日本にできないなずがない |
祥伝社
1999年2月 |
|
「現代のドイツ」
(事典・共著)
|
|
大修館書店
1998年8月 |
 |
「もどかしい親と
歯がゆい若者の国・日本」
|
何が日本をダメにしたのか。
信頼を回復したドイツ-急落する日本。
その根本の原因は=教育=にあった! |
祥伝社
1998年3月 |
 |
「歯がゆい国・日本」
|
なぜ私たちが冷笑され、ドイツが信頼されるのか。
あのイスラエルが今やドイツを信頼している!
同じ敗戦国同士でありながら、なぜこれほど国際的評価が違うのか |
祥伝社
1997年7月 |
|
「心に残る人びと」
(75人の中の1人)
|
|
文藝春秋
1996年12月 |
 |
「麻薬解禁」 |
豊かな国々を襲った退廃の極み・・・
厳罰主義が行き詰まった今日、残された道は解禁しかない。
日本も例外ではない。 |
講談社
1996年3月 |
 |
「統一ドイツ・新たなる苦悩」 |
ネオナチ台頭・渦巻く共感と不安、政治大国ドイツと小国日本 |
PHP研究所
1994年1月 |
|
「日本を変える200人の直言」
(共著)
|
|
産経新聞社
1993年1月 |
 |
「統一ドイツ・
その知られざる素顔」
|
ユダヤバチカン秘密警察・・・
21世紀の大国を動かす陰の力に、ドイツ在住20余念の著者が鋭く迫る。 |
PHP研究所
1992年7月 |
 |
「自由買い」 |
東ドイツの政治犯はこうして西ドイツ政府に買われた! |
文藝春秋
1986年3月 |
|
「ドイツに暮らす」 |
|
三修社
1983年10月 |
 |
「幸せへの前奏曲」
ドイツで頑張ってマス
|
飛び立とうとして飛べない彼女たち!幸福への回り道!
西ドイツの商都フランクフルト在住15年の著者が、その豊かな経験をもとに隣人、知人たちの姿をあたたかい眼差しで描く好著!
|
三修社
1983年 |
![]()
![]()
![]()